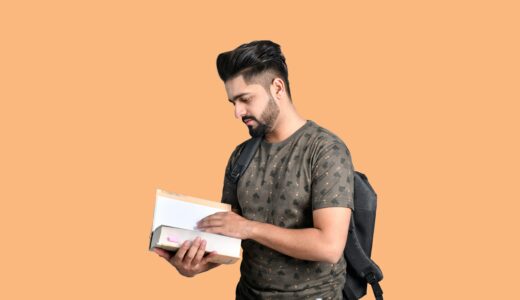壊さないことは、強くなることの一部。トレーニーのための予防学。
怪我を防ぐことは、“続ける技術”だ
トレーニーにとって、怪我は成長を止める最大のリスク。
一度の怪我で、数週間、数ヶ月の積み重ねが水の泡になることもある。
「怪我したら休めばいい」
それでは、強さは積み上がらない。
大切なのは、怪我を“しない身体”をつくること。
筋肉と同じように、怪我予防もまたトレーニングの一部だ。
ここでは、怪我を防ぐために必要な知識と視点を整理していく。
1. 怪我しやすい部位とは|“壊さない技術”を知る
鍛えるほど、関節や腱には見えない負荷が蓄積していく。
“強くなる”とは、同時に“壊さない”ための技術を身につけること。
代表的な怪我リスクの高い部位と原因・種目を以下にまとめた。
肩(ショルダー)
- 危険要因: インピンジメント症候群、回旋腱板炎
- 関連種目: ベンチプレス、ショルダープレス、サイドレイズ
※肩を傷めると「押す・引く・持ち上げる」すべてに影響が出る。
トレ全体にブレーキがかかるからこそ、最優先で守りたい部位。
腰(ローワーバック)
- 危険要因: 椎間板ヘルニア、筋膜性腰痛、脊柱起立筋の過負荷
- 関連種目: デッドリフト、スクワット、ベントオーバーロウ
※フォームの崩れ=一発アウトになりかねない。
回復に時間がかかるため、最も慎重に扱うべき部位のひとつ。
肘・手首(アーム・リスト)
- 危険要因: テニス肘、ゴルフ肘、手首の圧迫ストレス
- 関連種目: トライセプス系(ナローベンチ、フレンチプレス)、プレス全般
※手首は“消耗品”。違和感が出たら、無理せず立ち止まる勇気も必要。
膝(ニー)
- 危険要因: 靭帯損傷、半月板損傷、膝蓋腱炎(ジャンパー膝)
- 関連種目: スクワット、ランジ、ジャンプ系トレ
※膝を壊せば、「歩く・立つ」基本の動きさえ困難になる。
“脚全体で動く”意識が、最大の予防。
各部位のリスクを“感覚”ではなく、“根拠”で理解しておくこと。
それが、トレーニーとしての土台になる。
2. 怪我しやすい種目とは|“効かせる前に、安全に”

Photo by Shoham Avisrur on Unsplash
どれだけフォームが良くても、そもそも怪我リスクの高い種目は存在する。
筋肉への刺激が大きい分、フォームの崩れや疲労の蓄積がダイレクトに怪我に繋がる。
ここでは「気をつけたい代表的な種目」と「よくあるミス」を紹介する。
ベンチプレス
- リスク部位: 肩、手首、胸
- 注意点:
・バーを下ろす位置がズレると肩の負担が増大
・手首が寝すぎると、支える筋群に無理がかかる
改善ポイント:
・バーは「みぞおち〜乳頭ライン」に下ろす
・手首は真っ直ぐに保ち、リストラップで固定
デッドリフト
- リスク部位: 腰、肩甲帯、ハムストリング
- 注意点:
・背中が丸まる
・引く位置が足から離れすぎる
改善ポイント:
・セット前に「お腹に力を入れて胸を張る」
・バーは「すねをなぞる」ように引き上げる
スクワット(バーベル)
- リスク部位: 腰、膝、足首
- 注意点:
・腰が反りすぎ、または丸まりすぎる
・つま先と膝の方向がズレる
改善ポイント:
・背骨はナチュラルカーブを保つ
・膝とつま先を「同じ方向」に向ける
サイドレイズ
- リスク部位: 肩(特にインピンジメント)
- 注意点:
・重量が重すぎて、反動で持ち上げてしまう
・腕を上げすぎて肩関節に詰まりが出る
改善ポイント:
・肘を軽く曲げて、“肩で上げる感覚”を意識
・水平より「やや下」で止める
フレンチプレス(ライイングトライセプスエクステンション)
- リスク部位: 肘
- 注意点:
・肘が開きすぎて、負荷が分散される
・可動域を広げすぎて関節にストレスがかかる
改善ポイント:
・肘の位置を固定し、内側に締める
・“ストレッチ感”を出しすぎない
どんな種目も「効かせる」ことと「守る」ことのバランスが必要。
効かせる=追い込むではなく、
“適切にコントロールできる重さとフォームで”追い込むこと。
それが、怪我なく長く続けるためのトレーニング哲学だ。
3. 怪我の“予兆”を見逃さない

Photo by Salah Ait Mokhtar on Unsplash
違和感は、体からのサイン。
怪我の多くは、「いきなり」ではない。
むしろ、体は前もって何らかのサインを出している。
- いつもより疲労感が残る
- 関節に小さな違和感がある
- フォームがどこか安定しない
- なぜか集中できない
- ふと「今日はやめた方がいいかも」と感じる
こうした“違和感”は、根性で乗り越えるべきものではない。
気のせいじゃないか?と思うときほど、慎重でいい。
“気のせい”にしない習慣を持つ
トレーニングを継続する人ほど、自分の体に詳しくなる。
でもそれは、「痛くなってから」気づくのでは遅い。
- 朝起きたときに、肩や腰に違和感があるなら、その日は引く
- セットを重ねるごとに不安感が増すなら、種目を変える
- 1RM(最大重量)を更新する前に、調子を“問う”
自分の状態を日々チェックする習慣が、長く続ける人の共通点。
判断に迷ったら「軽くする」or「やらない」
迷ったときの選択肢は、たった2つ。
軽くするか、やらないか。
それだけで、怪我のリスクは大きく減らせる。
“その一回”を全力でやることより、
“10年後もトレーニングを続けている”ことの方が価値がある。
4. 守る工夫は、続ける工夫

Photo by Vitaly Gariev on Unsplash
“攻め”と“守り”は、セットで整える。
トレーニングには、攻める時間が必要だ。
でも、攻めるだけでは長く続かない。
体を守る工夫は、自分を守る知恵でもある。
そしてそれは、継続のための“仕組み”だ。
ウォームアップは「調整」でもある
筋温を上げ、関節の可動域を広げるだけじゃない。
自分の“今日の調子”を見極める時間でもある。
- 肩まわりが張っているか?
- 体が重くないか?
- どの種目で違和感が出るか?
自分をチェックしながら、スイッチを入れる。
5〜10分の準備が、怪我を遠ざける。
フォームに迷ったら「動画で見る」
やっているつもりと、実際のフォームは違うことがある。
- しゃがみが浅くなっていたり
- 腰が反りすぎていたり
- 左右差が出ていたり
主観では気づけない違いも、動画なら見える。
月に一度でも、自分の動きを客観視しておくと
フォームの“ズレ”を早期に修正できる。
軽めの“メンテナンス日”を組む
怪我予防は、「やらない日」だけではない。
軽めに“動かす日”を入れることで、ケアにもなる。
- 軽い重量でのフォーム確認
- ストレッチや動的ドリル中心の日
- 体幹や弱点部位を鍛える日
それは休みではなく、“整えるトレーニング”だ。
回復と成長を促す、もうひとつの仕組み。
5. 怪我を遠ざける人が持つ“視点”
「トレーニング=怪我と隣り合わせ」ではない。
本当に強い人は、こう考えている。
「怪我は“起こるもの”ではなく、“防げるもの”だ」と。
その意識の違いが、行動の違いを生み出す。
そしてその行動の積み重ねが、長く鍛え続ける力になる。
トレーニングは「自己管理力」でもある
自分の体に何が起きているのか。
いま必要なのは、追い込むことか、整えることか。
“正解”は外ではなく、自分の中にある。
- 周りに流されない
- 焦って無理をしない
- 地味なケアも、ちゃんとやる
強さとは、律する力でもある。
「続ける」ことが、一番の成果
怪我をしないことは、地味で目立たない。
でも、それが一番大きなリターンを生む。
- 自信がつく
- 習慣が積み上がる
- 理想の体に近づく
結果を出す人ほど、「怪我をしない仕組み」を持っている。
トレーニングを生活に根づかせるために──
“守る視点”を、手放さないでほしい。
まとめ

Photo by Giorgio Trovato on Unsplash
攻めるだけでは、続かない。
守るだけでは、変わらない。
大切なのは、「どちらも選べる状態」を持つこと。
今日攻めるのか、整えるのか。
その選択ができる人こそ、強くなれる。
怪我を“偶然”ではなく、“選択”で遠ざける。
それが、AGFが考える「鍛える力」だ。
NEXT STEP