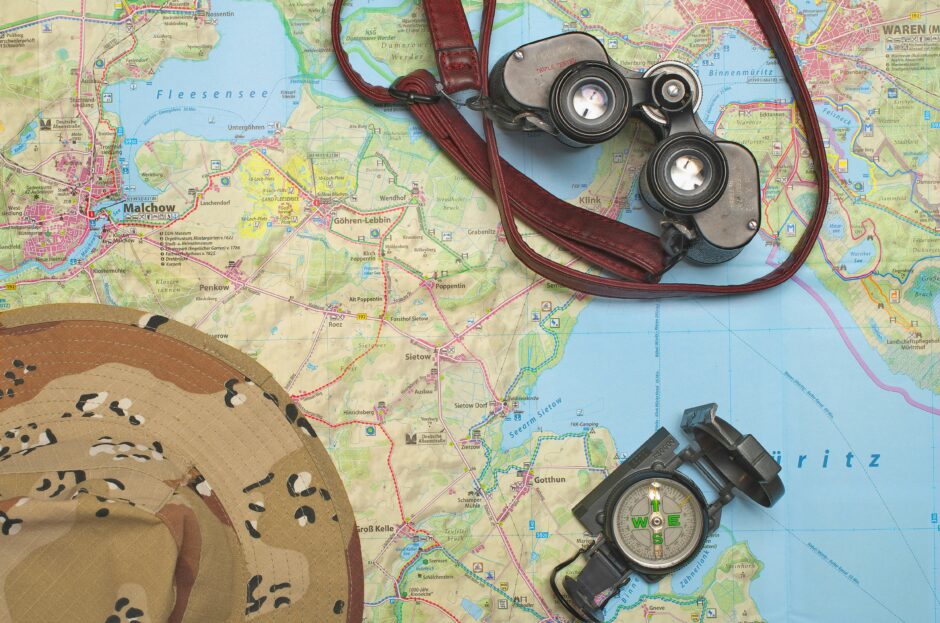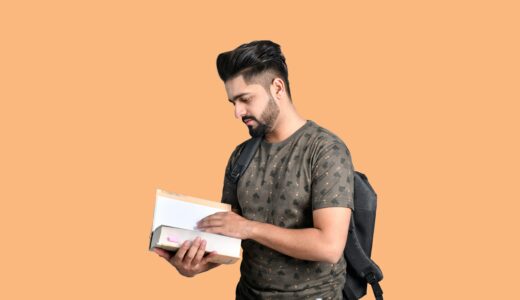目指す体がないトレーニングは、地図のない航海。
ただ何となく筋トレを続けている。
そんな人も多いはずだ。健康のため、習慣だから、ストレス解消として——理由はそれぞれある。
けれど、少しずつでも体が変わっていくにつれて、こう思う瞬間が来る。
「自分は、どんな体になりたいんだろう?」
目指す体があると、トレーニングは一気に意味を持ち始める。
鍛える順番、やるべき種目、食事の方針。すべてが“その体に近づくための選択”に変わる。
逆に、目指す体が曖昧なままでは、努力の方向性もブレやすい。
筋トレとは、言い換えれば「自分の体をどこへ向かわせるか」という旅だ。
だからこそ——筋トレにも、地図が必要だ。
この記事では、トレーニーが目指すことの多い体型を6つのスタイルに分けて紹介する。
それぞれの特徴、向いている人、トレーニングや食事の方向性、
そして「今どんな体からスタートするか」で変わる進め方まで丁寧に解説していく。
自分がどんな体を目指したいのか。
そのゴールを定めることが、鍛える理由に芯を与えてくれるはずだ。
1. アスリート型|“動ける体”を目指す
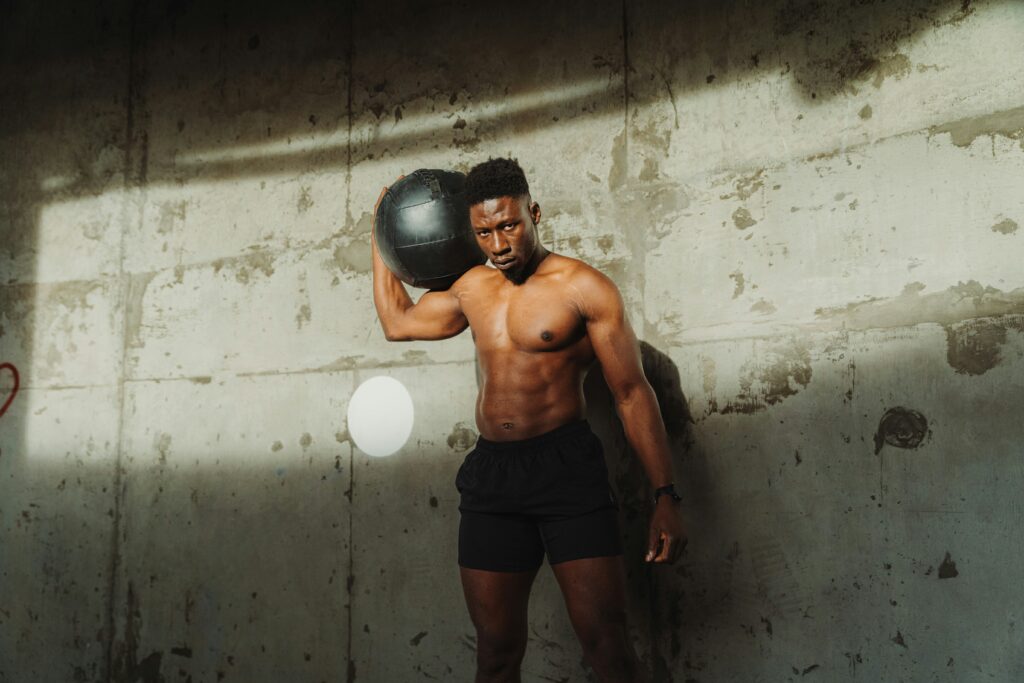
Photo by Arthur Edelmans on Unsplash
体の特徴と魅力
このスタイルの最大の特徴は、機能美。
見た目の派手さよりも、「走る・跳ぶ・闘う」といった動作の中で発揮される本物の強さが宿る体だ。
脂肪が少なく、引き締まった筋肉。過度な肥大はなく、全身がバランスよく整っている。
筋肉を“見せる”ためではなく、“使う”ために鍛えられた体は、見る人にも自然な説得力を与える。
向いている人/憧れの人物像
- スポーツや格闘技に関心がある人
- 「機能する筋肉」を大切にしたい人
- 引き締まって動ける体を目指したい人
たとえば、格闘家、ラグビー選手、サッカー選手、スプリンターなどに憧れるなら、このスタイルが近い。
現代フィットネスで人気の「ファンクショナルトレーニング」や「アスレティックパフォーマンス系の筋トレ」も、この路線に含まれる。
目指すためのトレーニング
- 高重量よりもスピードやフォーム重視
- 複合関節種目(スクワット、懸垂、ベンチプレス、クリーン系など)
- スプリント、ジャンプ、サーキットトレーニング、HIITなども有効
下半身・体幹の強さが要となる。
日常動作やスポーツに直結する動きを鍛えながら、バランスよく全身を整える。
目指すための食事戦略
- 筋量の維持とパフォーマンスの維持を両立するため、高タンパク中炭水化物型
- 減量ではなく、余分な脂肪をつけずに筋肉を活かす食事設計
- トレーニング前後の栄養補給(カーボ+タンパク)を重視
食事は「筋肉のため」だけでなく「動ける状態を維持するため」にある。
スタート地点によって変わるルート
- 痩せ型の人は:まずは全身の筋力をしっかりとつける。特に脚と体幹を優先的に鍛え、動ける体の土台をつくること。
- 脂肪が多めの人は:減量と有酸素を取り入れつつ、スピードや敏捷性にフォーカスした筋トレを並行して行う。余分な脂肪が落ちれば、キレのある動きと体型が両立できる。
- 運動未経験の人は:最初は基礎動作(スクワット、プッシュアップなど)や軽いサーキットから。無理なく動ける身体を“つくりながら慣らす”。
アスリート型|まとめ
“動ける体”は見た目に派手さこそないが、生活の中でこそその真価を発揮する。
荷物を軽々と持ち上げ、全力で走れ、転ばず踏ん張れる。そんな機能性に満ちた体は、筋トレの最終形のひとつとも言える。
目指すのは、見た目より動ける実感。
筋肉を“使える状態”で持つこと。それがアスリート型の美しさだ。
2. フィジーク型|黄金比をまとう体

Photo by Total Shape on Unsplash
体の特徴と魅力
この体型のキーワードは“黄金比”。
広い肩幅、厚みのある胸、引き締まった腹筋、そして絞られたウエスト。
いわゆる“逆三角形”のシルエットが最大の魅力であり、完成度の高い見た目を追求するスタイルだ。
筋肉のサイズはもちろん重要だが、それ以上にバランスと美しさが問われる。
ステージやビーチで映える“見せる筋肉”を、計画的に育てていく。
向いている人/憧れの人物像
- ボディラインにこだわりたい人
- 美意識を持って鍛えたい人
- 「かっこいい体」を客観的に評価されたい人
コンテストでの評価基準にもなっているため、審美的な体作りを目指す人には最適。
憧れの対象としては、クリス・バムステッド(クラシック寄り)、国内のフィジーカー、筋肉系インフルエンサーなどが挙げられる。
目指すためのトレーニング
- 背中・肩・胸のアウトラインを際立たせるトレーニングが中心
- 部位別で丁寧に鍛える分割法が基本(例:胸・背中・肩・腕・脚)
- 有酸素も入れながら体脂肪率を落とす意識も必要
特に背中(広背筋)と肩(三角筋)の横幅は重要なポイント。
全体のバランスを壊さずに、必要な部位を重点的に鍛える戦略性が求められる。
目指すための食事戦略
- バルク期と減量期を使い分け、計画的に体をつくる
- 増量中でも“脂肪をつけすぎない”クリーンな食事
- 減量期はPFCバランスを調整し、筋肉を落とさず絞ることがカギ
ボディメイクにおいては、「食事の管理力=仕上がりの美しさ」と言っても過言ではない。
スタート地点によって変わるルート
- 痩せ型の人は:まずはバルク優先。特に肩・背中・胸を重点的に大きくして、土台を広げること。
- 脂肪が多めの人は:クリーンな減量からスタート。筋肉のアウトラインが見え始めた段階で、部位別強化に切り替えるとスムーズ。
どちらにしても「絞る⇄つける」の切り替えが重要であり、長期的な目線で戦略を組むことが求められる。
フィジーク型|まとめ
フィジーク型は、“筋肉の造形”を極めるスタイルだ。
トレーニングも食事も、ただ頑張るのではなく、「どう見せたいか」から逆算して設計する。
見た目へのこだわりは、決して軽視すべきものではない。
それは自分をどう在りたいか、どう表現したいかという美意識の表れでもある。
フィジーク型を目指すことは、体を通じたアートを創る行為でもあるのだ。
3. ボディビルダー型|圧倒する体

Photo by SAJAD RADEY on Unsplash
体の特徴と魅力
このスタイルの特徴は、とにかく“大きい”こと。
鍛え抜かれた筋肉が全身に詰まり、どの角度から見ても「強さ」と「存在感」がにじみ出る。
ただ大きいだけではない。筋肉のセパレーション、カット、厚み、そして“異常なまでの完成度”。
それらが合わさったとき、見る者を圧倒する“芸術的な肉体”が立ち上がる。
この体型は、サイズ・密度・極限の仕上がりを追求する者だけが辿り着ける領域だ。
向いている人/憧れの人物像
- 筋トレが人生の一部になっている人
- 「どこまでデカくなれるか」に魅せられている人
- コンテスト出場や究極の肉体を目標にしている人
アーノルド・シュワルツェネッガー、ビッグ・ラミー、山岸秀匡など、真のボディビルダーに憧れを抱くなら、この道に進む価値がある。
筋肉の“美”ではなく、“圧”を追い求めるスタイルだ。
目指すためのトレーニング
- 高重量×高ボリュームの圧倒的なトレーニング量
- パーツごとの細かい鍛え分け(上部・中部・下部、内側・外側など)
- 分割法が基本で、部位ごとの回復と刺激のバランスが重要
一部ではなく全身をまんべんなく巨大化させる必要があるため、計画性と反復がすべて。
刺激の“質”を高める意識も求められる。
目指すための食事戦略
- バルク期は高カロリー・高タンパク+クリーンな食材で筋肉を伸ばす
- 減量期はハードな絞り込みが求められ、摂取カロリーと代謝のせめぎ合い
- サプリメントの活用も必須レベル(プロテイン、クレアチン、EAAなど)
この体を目指すには、食事もまたトレーニングの一部だと捉える必要がある。
スタート地点によって変わるルート
- 痩せ型の人は:とにかく“食べて、重いものを挙げる”ことから始まる。筋量を伸ばす時期を1〜2年単位で考える。
- 脂肪が多めの人は:減量しながらも筋肉量を保つ“ボディメイク型のトレーニング”で徐々に基礎を築く。焦らず、まずは筋肉の存在感を引き出すところから。
いずれにしても、長期戦覚悟のアプローチになる。日々の積み重ねと忍耐力が試される世界だ。
ボディビルダー型|まとめ
この体を目指すことは、筋トレに人生を賭けるようなものだ。
日常生活のあらゆる選択が「筋肉のため」になる。時間、食事、休養、すべてを筋肉に捧げる日々。
だからこそ、体に宿る筋肉は“結果”ではなく、“生き方”そのもの。
圧倒的な体は、言葉より雄弁に、男の覚悟を語る。
4. モデル・細マッチョ型|軽やかに鍛える体
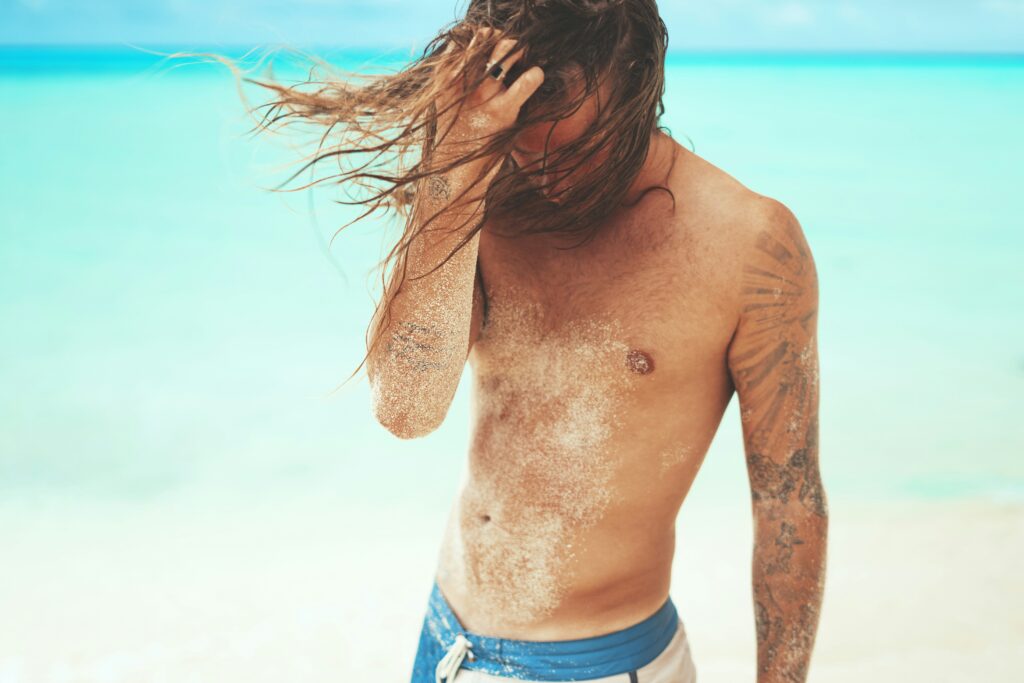
Photo by Marvin Meyer on Unsplash
体の特徴と魅力
この体型の魅力は、「軽さ」と「輪郭」だ。
脂肪が少なく、輪郭のはっきりした筋肉が体にうっすらと浮かぶ。
しかしゴツすぎず、服を着ても映える、脱いでも説得力のある体。それがこのスタイルの強みである。
筋量よりも全体のシルエットやバランスが重視される。
とにかく“ちょうどいい”、そんな言葉が似合う体型だ。
向いている人/憧れの人物像
- モデル、俳優、K-POPアイドルのような体に憧れる人
- 服をおしゃれに着こなしたい人
- 無理なく続けられるスタイルを作りたい人
「筋トレはしたいけど、ムキムキにはなりたくない」
そう思っている人にこそ、このスタイルは最適だ。
目指すためのトレーニング
- 基本は全身をまんべんなく鍛えるメニュー(自重トレでもOK)
- 高重量よりもフォーム・回数・テンポ重視
- 有酸素運動との相性も良く、体脂肪をコントロールしやすい
ベースとしては筋トレ初心者向けの王道種目(スクワット、プッシュアップ、懸垂など)を軸にしつつ、体型維持が目的のメニューに調整していく。
目指すための食事戦略
- 体脂肪をためない食習慣の確立が最重要
- 過剰に食べず、タンパク質と野菜をベースにした“整った食事”
- たくさん食べて大きくなるより、「無駄なく維持する」方向性
極端なバルクアップや減量は不要だが、体脂肪率を10〜15%程度にキープする意識は必要。
スタート地点によって変わるルート
- 痩せ型の人は:食事量をやや増やしつつ、全身の筋肉に少し厚みを持たせる。無理に“増量”せず、体重はゆるやかに上げるのがコツ。
- 脂肪が多めの人は:有酸素と筋トレを並行して取り入れ、体脂肪率を落とす。筋肉がうっすら見えるだけで、印象は大きく変わる。
この体型に必要なのは、“目立たない努力”を積み上げることだ。
モデル・細マッチョ型|まとめ
モデル・細マッチョ型は、“なにげなく整っている”という美しさを持っている。
そのさりげなさの裏にあるのは、日々の節制と丁寧な習慣だ。
筋トレは、大きくなるためだけのものじゃない。
この体型が示しているのは、筋肉も、美も、引き算で作れるということだ。
5. 競技型(リフター型)|力に特化した体
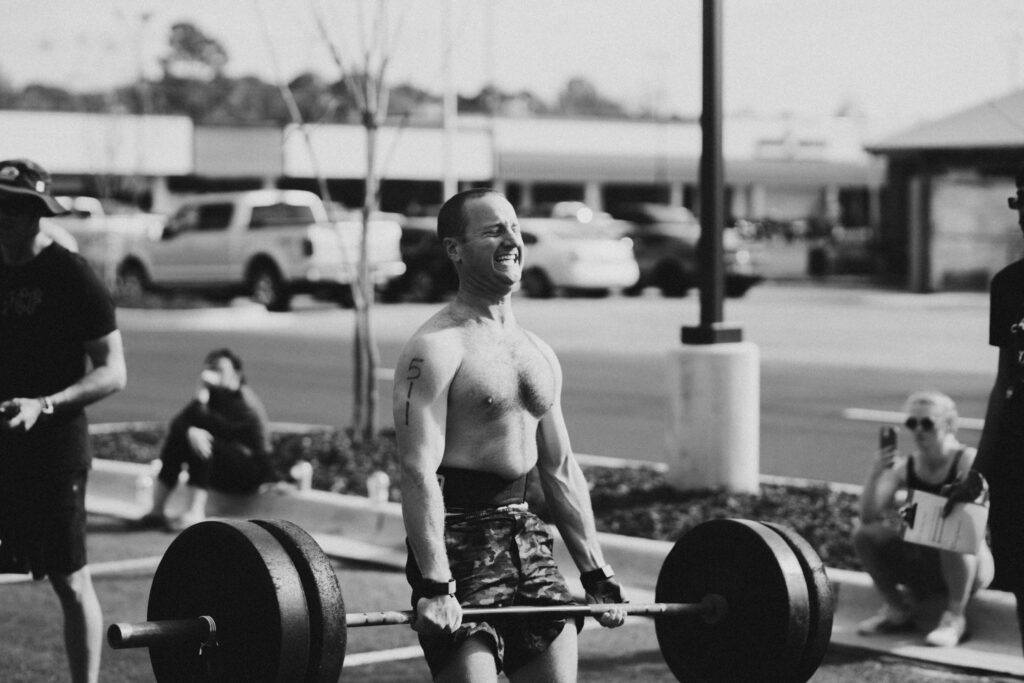
Photo by Corey Young on Unsplash
体の特徴と魅力
この体型は、何よりも“出力”を重視する。
どれだけ重いものを挙げられるか。どれだけ正確に力を伝えられるか。
それがすべてであり、見た目ではなく「記録」が評価基準だ。
競技レベルに応じて体型は様々だが、共通しているのは「動作効率に最適化された肉体」。
柔軟性・安定性・爆発力を備えた、実戦仕様のパワー体型である。
向いている人/憧れの人物像
- 重量を伸ばすことにやりがいを感じる人
- パワーリフターやウェイトリフターに憧れる人
- 記録や競技に目標を持ちたい人
「デッドリフトで200kgを挙げたい」
「スナッチやクリーン&ジャークを極めたい」
そんな目的があるなら、このスタイルはしっくりくるはずだ。
目指すためのトレーニング
- 神経系の出力を高める低回数・高重量のプログラム
- フォーム練習を重ねる“競技的トレーニング”(特にオリンピックリフティング)
- 可動域・安定性・補助種目の精密な設計も不可欠
スクワット・デッドリフト・ベンチプレスなどのビッグ3を軸に、
“力をどう出すか”に徹底的に向き合う。
目指すための食事戦略
- 筋量よりもパフォーマンス維持のためのエネルギー補給
- 増量は無理にせず、階級や動きやすさと相談しながら体重管理
- 競技日程やトレーニング強度に合わせた柔軟な食事設計が求められる
このスタイルでは、食事は「筋肉のため」よりも「記録のため」に存在する。
スタート地点によって変わるルート
- 痩せ型の人は:まずは“動作を覚えること”から。フォーム練習と食事による体重増加で安定感を高める。
- 脂肪が多めの人は:一気に絞らず、競技パフォーマンスを落とさない範囲で少しずつ体を動かし、使える筋肉に変えていく。
見た目にとらわれず、記録を追う覚悟があるかどうかがこのスタイルの前提となる。
競技型(リフター型)|まとめ
競技型の体は、ある意味で最もストイックだ。
筋肉の形も脂肪の有無も関係ない。ただ「どれだけ力を出せるか」。
その一点に、日々のトレーニングと食事が向かっていく。
記録という明確な目標があるからこそ、体は磨かれ続ける。
他人にどう見られるかではなく、自分がどう“強く”なったかを問う体型である。
6. ウェルネス型|整える体

Photo by Michael DeMoya on Unsplash
体の特徴と魅力
この体型は、“調子がいい”をつくることが目的だ。
派手な筋肉や目立つアウトラインではなく、呼吸の深さ、睡眠の質、朝の目覚めの軽さ、姿勢の美しさ…。
そういった日常の“感覚”にこそ、この体型の価値がある。
いわば、見た目のためではなく、人生の土台としての身体を整えるスタイル。
気づけばお腹が凹み、肌ツヤも良くなり、疲れにくくなる。
そんな“静かな変化”が、最大の成果となる。
向いている人/憧れの人物像
- 健康の不調をきっかけに筋トレを始めた人
- 姿勢や肩こり、疲れやすさなどに悩んでいる人
- 無理なく、でも本質的に自分を変えたい人
理学療法士や機能改善系のトレーナー、ウェルネス志向のインフルエンサーに惹かれるなら、このスタイルはしっくりくる。
筋肉は“戦うための鎧”ではなく、“自分を整えるための支え”となる。
目指すためのトレーニング
- 筋トレは“目的”ではなく“手段”として活用
- 体幹トレーニング、正しいフォームでの自重種目が基本
- 柔軟性や可動域を整えるストレッチ・モビリティワークも重視
「今日は何キロ挙げたか」ではなく、「今日は身体がどう動いたか」が成果になる。
筋トレはもちろん行うが、量より質、重量より意識の世界だ。
目指すための食事戦略
- 栄養バランスを重視し、加工品を減らして“整った内臓”を育てる
- 過度な糖質制限や極端な食事は行わず、持続可能な“整食”を目指す
- 消化力、睡眠、肌・便通など「体の声」に敏感になるのが鍵
目的はダイエットではなく、“体調の土台”をつくること。
その結果として、自然と見た目にも変化が現れる。
スタート地点によって変わるルート
- 生活習慣が乱れている人は:まずは“朝の光・食事・睡眠”の3点を整えるところから。体調が整うだけで、動きたくなる体に変わってくる。
- 姿勢や不調がある人は:いきなり筋トレよりも、ストレッチや体の使い方を整えることから始める。土台が整えば、自然と鍛えられる体になる。
体調・可動域・呼吸・生活のリズム。これらすべてが“あなたの今”を表している。
ウェルネス型|まとめ
ウェルネス型は、最も地味で、最も深い体型かもしれない。
それは「何かのために鍛える」のではなく、「自分と向き合うために整える」行為。
日々の調子が整い、毎日がすこしずつ楽になる。
その先に、あなたらしい美しさと強さが育っていく。
まとめ
筋トレは、ただ筋肉を増やすためのものじゃない。
どんな体で生きていきたいか。どう在りたいか。
それを形にしていく、ひとつの“デザイン手段”だ。
人によって目指す体は違う。
圧倒的な筋量を追い求める者もいれば、整った姿勢や心地よい体調を目指す人もいる。
動ける体。見せる体。服をかっこよく着る体。疲れにくい体。
どれが正解でも間違いでもなく、すべては自分の“理想”から始まる。
そして理想が定まれば、努力はブレなくなる。
今日のトレーニングにも、食事にも、休養にも意味が宿る。
そうして積み上がった日々が、やがてあなた自身を語る体になる。
まずは、自分の地図を描こう。
そこからすべてが始まる。
NEXT STEP