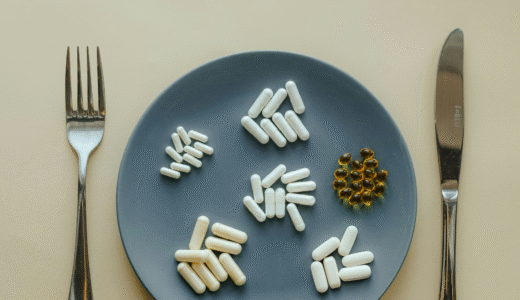毎日食べるからこそ知っておきたい。自然の恵みとどう向き合うか
鶏むね肉は、トレーニーにとって欠かせない存在です。
高たんぱく・低脂質でコストも低く、減量中でもバルク中でも活躍してくれる食材の代表格でしょう。
しかし、そんなむね肉にも、思わぬ“当たり外れ”があります。
どれだけ丁寧に火入れをしても、どうしても食感が悪くなることはありませんか?
パサパサを通り越して、ゴリゴリ。繊維が粗くて噛み切りにくい。
その原因は、調理ミスではなく「ウッディ・ブレスト(Woody Breast)」と呼ばれる筋肉異常かもしれません。
ウッディ・ブレストとは?

Photo by Eiliv Aceron on Unsplash
ウッディ・ブレストとは、ブロイラー(食肉用の品種改良された鶏)に見られる筋肉障害のひとつです。
急速な成長により胸筋が過剰に肥大し、血流や酸素供給が追いつかず、筋繊維の壊死や線維化が起きます。
これにより、肉質が木のように硬くなり、ゴリゴリとした食感になります。
実際の研究では、影響を受けた筋肉では以下のような変化が確認されています:
- 筋細胞の壊死と線維化(コラーゲン沈着の増加)
- カルシウム濃度の異常上昇
- 酸化ストレスの増加
- 脂質代謝の乱れ
これらの要素が複合的に関与し、食感や栄養面に影響を及ぼしています。
トレーニーにとっての問題
この問題が特に深刻なのは、鶏むね肉を日常的に食べているトレーニーにとってです。
消費量が多ければ、その分ウッディ・ブレストに当たる確率も上がります。
この異常は加熱後に初めて気づくことも多く、該当部分は食べられずに廃棄せざるを得ません。
そうなると、予定していたタンパク質摂取量が確保できなくなり、栄養管理にズレが生じることになります。
日々のコンディションを整えている人ほど、この外れ肉は小さくない問題になるはずです。
どんなときに当たりやすい?
ウッディ・ブレストの発生率については、軽度なものを含めれば鶏むね肉全体の35〜50%にのぼるという研究報告もあります。
つまり、決して珍しい現象ではなく、むしろ「当たり前に存在している問題」と言えます。
実際の経験としても、グラム数の大きいむね肉(特に400g以上)ほど当たる確率が高いと感じる人は多いはずです。
これは急成長による負荷のかかりやすさと関係している可能性があります。
また、「ブランド鶏」や「国産の高品質な鶏肉」は比較的当たりにくいとされ、
アメリカの消費者向けメディアでも「小さめの鶏むね肉を選ぶのが効果的」と紹介されています。
避け方と、当たったときの対応
【避け方】
- パック内で不自然に盛り上がっているものは避ける
- 指で押したときに硬さやゴリつきを感じたら回避
- 大きすぎるサイズ(特に400g以上)は注意
- 品質の安定したブランド鶏や産地を選ぶ
【当たったとき】
- 異常な部位は無理に食べず、潔くカットして捨てる
- ゆで卵・豆腐・ギリシャヨーグルト・プロテインなどでその日のタンパク質をリカバリー
- むね肉をまとめて調理しておくと、1枚外れても他でカバーできる
食への感謝と、自然との付き合い方

Photo by Krishna K. Maiti on Unsplash
ウッディ・ブレストは、食べ物としての「質」を下げる原因となりますが、人体への害はありません。
むしろ、こうした問題が起こる背景には、効率化や大量生産の副作用があることを忘れてはいけません。
自然の恵みを、より安く・便利に手に入れようとする流れの中で、
筋肉の構造が崩れ、トレーニーにとっての“主力食材”が思わぬ形で揺らいでいる。
そう考えると、食材選びにも少しだけ目を向けておきたくなります。
結びに
トレーニーにとって、鶏むね肉は体をつくる土台です。
でも、いつも完璧な状態の肉が届くとは限りません。
自然由来のものは、完全にコントロールできない。
それは、食材だけではなく、自分の体調や気分にも通じる感覚です。
日によって調子が違うのも、むね肉に“当たり外れ”があるのも、ある意味では自然なことなのかもしれません。
低コストで手に入る便利さを選ぶのか、品質にこだわって安心を選ぶのか。
どちらも間違いではなく、大切なのは「知った上で選べること」です。
知識と経験で、今日の食事をうまく整えていきましょう。
NEXT STEP