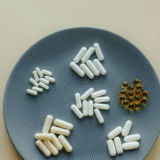筋肉より先に、心を鍛えよ。2000年前のローマからの教え
トレーニングは、心との戦いだ。
ジムに行く気が起きない朝。減量中に差し出される甘い誘惑。成果が出ず、焦りや苛立ちに飲まれそうな日。
そんなとき必要なのは「動じない心」だ。
その答えを示した人物がいる。
ローマ帝国の皇帝にして、哲学者でもあったマルクス・アウレリウス。
彼は戦場にありながら哲学を綴り、自分を律することをやめなかった。
目次 閉じる
マルクス・アウレリウスという男
紀元121年生まれのローマ皇帝。
贅を避け、ストア派哲学を信じ、自分を厳しく律した。
戦場の夜、彼は『自省録』を記した。
それは臣下への命令書ではなく、自分に向けた言葉だった。
「怒りを鎮めよ」「理性を選べ」「他人に左右されるな」
混乱や戦争、疫病のただ中で、彼は心を鍛え続けた。
哲学の言葉とその意味

Photo by Anastasiya Badun on Unsplash
外側の出来事は人を傷つけない
起こった出来事そのものではなく、それをどう受け取るかが苦しみを生む。
外部の刺激に振り回されるかどうかは、自分次第だ。
今この瞬間に最善を尽くせ
過去や未来にとらわれず、目の前の義務に集中する。
人生は思い通りにならない。だからこそ「今」に力を注ぐ。
恐れるべきは死ではなく、生き方を恐れること
他人の評価や失敗を恐れて動けないこと。
それこそが、本当に恐れるべき生き方の欠落だ。
トレーニーにどう活かすか
外側の出来事は人を傷つけない
減量中の空腹、停滞期、周囲の言葉。
心を揺らす要因は多いが、どう反応するかは自分が決められる。
環境に振り回されず、自分の軸を持つことが強さになる。
今この瞬間に最善を尽くせ
1ヶ月後の見た目や、過去の失敗を悔やんでも何も変わらない。
今日のトレーニングを全力でやりきること。
それだけが未来をつくる。
恐れるべきは死ではなく、生き方を恐れること
大きな重量に挑むこと、人前でのフォーム、食事の制限。
それを避けるのは「評価を恐れる心」だ。
アウレリウスは教える。恐れるのは失敗ではなく、挑戦しない生き方だと。
結び

Photo by Brendan Stephens on Unsplash
マルクス・アウレリウスは、皇帝でありながら自分に最も厳しかった。
贅沢に流されず、戦場でも哲学を実践し続けた。
トレーニーにとっても同じだ。
筋肉を鍛えるだけでなく、心を鍛えることが最大の武器になる。
彼の教えは、次の3つにまとめられる。
• 環境に振り回されないこと。
• 今日を選び抜くこと。
• 挑戦を恐れないこと。
それが、2000年前の皇帝から受け継げるトレーニーの哲学だ。
参考文献・参考サイト
- Marcus Aurelius, 『自省録』岩波文庫
- Marcus Aurelius, Meditations(英語原典)
- スタンフォード哲学百科事典(Stanford Encyclopedia of Philosophy)|Marcus Aurelius
https://plato.stanford.edu/entries/marcus-aurelius/ - ウィキペディア(日本語版・英語版)|https://ja.wikipedia.org/wiki/マルクス・アウレリウス・アントニヌス
- Donald Robertson, How to Think Like a Roman Emperor: The Stoic Philosophy of Marcus Aurelius
NEXT STEP