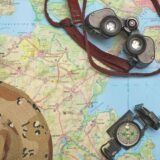トレーニーに特有の体の不調とその原因・対策を、9つの視点から丁寧に解説。
筋トレをしているのに、なぜか体の調子がすぐれない。
肌は荒れ、便秘が続き、やる気が出ない。トレーニングの質も上がらず、疲れも抜けない。
これらの不調は、筋トレをしている人に特有のサインである可能性があります。
本記事では、トレーニーが陥りやすい体の不調を9つのテーマに分けて紹介し、それぞれの原因と具体的な対策を解説します。
筋肉だけでなく体全体を整えることで、トレーニングの成果をしっかり引き出していきましょう。
脂質不足が招く、肌荒れ・ホルモン不調

Photo by John Vid on Unsplash
減量中に脂質を大きく削る人は少なくありません。しかし脂質はホルモンの材料であり、皮膚のバリア機能や脳の働きにも欠かせない栄養素です。極端に不足すると、肌の乾燥や粉ふき、ニキビ、かゆみといった症状だけでなく、集中力ややる気の低下、睡眠の乱れにもつながります。
起こりやすい不調のサイン
- 肌の乾燥、粉ふき、ニキビ、かゆみ
- 集中力ややる気の低下
- 睡眠の質の乱れ、気分の不安定
摂りたい良質な脂質
- 青魚(サバ・イワシなど):EPA・DHA
- アボカドやナッツ類:不飽和脂肪酸、ビタミンE
- オリーブオイル、えごま油:オメガ3、抗炎症作用
脂溶性ビタミン(A・D・E・K)は脂質と一緒に摂ることで吸収率が高まり、肌や免疫の安定にもつながります。肌荒れやかゆみが長引く場合は、早めに皮膚科を受診しましょう。
脂質は「削る」のではなく「選ぶ」ものです。良質な脂を取り入れることで、体調とパフォーマンスを守ることができます。
→ 脂質については『脂質の教科書|筋肉・ホルモン・健康を守る油の話』も参考にしてください。
高タンパク食が腸を乱す

Photo by nilufar nattaq on Unsplash
筋肉を育てるために欠かせないたんぱく質。プロテイン、鶏むね肉、卵、ギリシャヨーグルトなどはトレーニーの定番です。ただし、たんぱく質ばかりに偏り、腸を整える栄養素が不足すると腸内環境は乱れやすくなります。
たんぱく質の分解には腸への負担が伴い、悪玉菌が増えることで便秘になりやすくなります。反対に、プロテインを牛乳で割る人は乳糖不耐症の影響で下痢を起こすこともあります。
起こりやすい不調
- 便秘や下痢が続く
- お腹の張りや不快感
- 肌荒れやニキビなど“外側のトラブル”
- イライラや気分の落ち込み
腸を守るために意識したいこと
- 食物繊維をプラス:野菜、海藻、きのこ、玄米、オートミールなど。不溶性+水溶性の両方を意識
- 発酵食品を習慣に:納豆、キムチ、ヨーグルト、味噌を“少しずつ毎日”
- プロテインの摂り方を調整:水で割る、植物性に切り替える、乳糖カットタイプにする
腸内環境の改善はすぐに見た目には出ませんが、心身の調子や肌、免疫力に確実に影響します。筋肉だけでなく、腸内細菌にも栄養を届ける意識を持つことが大切です。
→ タンパク質については『タンパク質の教科書|筋肉・回復・健康を支える“体の材料”』で詳しく説明しています。
サプリの過剰摂取に注意

Photo by Aleksander Saks on Unsplash
筋肉を育てるため、体調を整えるためにサプリメントを活用する人は多いです。BCAA、EAA、クレアチン、マルチビタミン、ZMA、プレワークアウトなど、正しく使えば効果があります。
しかし「効きそうだから」と無制限に摂り続けると、体に思わぬ負担をかけることがあります。特に脂溶性ビタミン(A・D・E・K)、鉄分、亜鉛などは体に蓄積しやすく、過剰摂取が害になることもあります。また、添加物や人工甘味料を多く含む製品は腸や肝臓への負担につながります。
起こりやすい不調のサイン
- 肌荒れや吹き出物が増える
- 胃のムカつきや消化不良
- だるさや頭痛が続く
- 尿の色やにおいの変化
見直したいポイント
- 自分に本当に必要なサプリを選ぶ
- 1日3種類以上摂っている場合は減らすことを検討
- 成分表示を確認し、人工甘味料・添加物の少ない製品を選ぶ
- 「なんとなく」飲み続けているものは一度やめてみる
サプリは薬ではなく、体を補うための手段のひとつにすぎません。体の声に耳を傾け、必要以上に足さないことが、不調を防ぐ最大のコツです。
→ サプリについては『トレーニーのためのサプリ完全ガイド|筋肥大・回復・減量に』でまとめています。
水分・電解質の不足がパフォーマンスを下げる

Photo by engin akyurt on Unsplash
高強度のトレーニングで汗をかいたあとに必要なのは、水分だけではありません。汗と一緒にナトリウム、カリウム、マグネシウムといった電解質も失われています。水だけを大量に飲んでいると、かえって体内バランスが崩れ、筋肉や神経の働きを妨げることがあります。最悪の場合は「隠れ脱水」のような状態にもつながります。
起こりやすい不調のサイン
- 脚がつる(こむら返り)
- トレーニング中や後の頭痛
- 倦怠感やトレーニングが重く感じる
- 寝汗で脱水気味になり、夜中にだるさを感じる
取り入れたい対策
- トレーニング中や後は、ミネラル入りドリンクを活用(塩をひとつまみ加えるだけでもOK)
- 夏場やサウナ後は特にマグネシウム・カリウムを意識して補給
- 食事では味噌汁、ぬか漬け、ナッツ類など自然に電解質を含む食品を選ぶ
水を飲んでも疲れが取れないと感じるときは、「電解質が足りているか」をチェックしてみてください。それだけでパフォーマンスや回復力が大きく変わります。
→ 夏場の栄養不足や脱水リスクについては『夏バテと筋トレ|失いやすい栄養と体調管理の盲点』、
または 『疲れが抜けないあなたへ。見落としがちな「ミネラル不足」のサイン』も参考になります。
エネルギー不足が心も体も壊す

Photo by Nubelson Fernandes on Unsplash
減量中はカロリーを抑えることが基本ですが、やる気がある人ほど「もっと削ろう」「もっと追い込もう」となりがちです。その結果、必要最低限のエネルギーすら足りなくなり、体調やパフォーマンスを大きく落とすことがあります。スポーツ医学では「相対的エネルギー不足(RED-S)」と呼ばれ、消費に対して摂取が大きく不足することで、身体機能そのものが低下する状態を指します。
起こりやすい不調のサイン
- トレーニングしても筋肉がつかない、むしろ減っていく
- 朝からだるく、無気力で集中できない
- イライラや気分の落ち込みが増える
- 風邪をひきやすく、回復が遅くなる
守りたい対策
- 基礎代謝+日常活動分は最低限確保する
- トレーニング前後はしっかり炭水化物を摂り、質と回復を支える
- 減量中でも「この量なら続けられる」という摂取ラインを守る
減量の目的は「痩せること」ではなく「筋肉を残して脂肪を落とすこと」です。削りすぎないこともまた、成果を出すための戦略になります。
→ エネルギー不足と不調の関係は『減量中に起こる“心と体の異変”とその対策』にもまとめています。
オーバーワークが不調を呼ぶ

Photo by Maciej Karoń on Unsplash
「筋肉は裏切らない」「努力は報われる」。そう信じて、疲れていてもジムに向かうトレーニーは少なくありません。ですが、休まない努力は努力ではなく、慢性的な疲労や不調の原因になります。トレーニングは筋肉にダメージを与える行為であり、回復してこそ成長します。回復が追いつかないまま続けると、パフォーマンスも筋肥大も頭打ちになり、体を壊す方向へ進んでしまいます。
起こりやすい不調のサイン
- 関節の痛み、慢性的な張り
- ジムに行くのが憂鬱、モチベーション低下
- 夜中に目が覚める、寝ても疲れが抜けない
- 些細なことでイライラする、落ち込みやすくなる
取り入れたい対策
- 筋肉痛が残っている部位は休ませる/別の部位を鍛える
- 週1日は完全休養日を設け、自律神経を落ち着かせる
- 睡眠の質を高める工夫(スマホ・カフェイン制限、寝る前のルーティンづくり)
休むことに罪悪感を持つ必要はありません。むしろ「もう少しいけるかも」のタイミングで休める人ほど、長く伸びていけるのです。
→ 実際に休むべきか迷うときは 『今日はジムを休むべきか、それとも行くべきか。』が参考になります。
腸が不調だと、肌も脳も不調になる

Photo by Shoham Avisrur on Unsplash
トレーニーの食事は高たんぱく・低脂質・低糖質を意識しがちで、プロテインやサプリも欠かせません。しかしその一方で、腸にとっては負担の大きい食生活になっていることがあります。
腸に負担をかけやすい食習慣
- 動物性たんぱく質に偏っている
- 食物繊維や発酵食品が不足している
- 人工甘味料や添加物の多いプロテインや加工食品を常用している
これらは腸内の悪玉菌を増やし、腸内フローラ(腸内細菌のバランス)を乱す原因となります。腸は「第二の脳」と呼ばれるほど心身に深く関わる臓器。乱れれば、肌やメンタルにも不調が広がります。
起こりやすい不調のサイン
- 便秘や下痢が続く
- ニキビや肌のくすみ、荒れが改善しない
- イライラや気分の落ち込み
- 風邪をひきやすく、回復が遅い
- 疲労感が抜けない、睡眠が浅い
整えるために意識したい習慣
- 食物繊維(特に水溶性)を摂る:わかめ、もち麦、オクラ、納豆、りんご、バナナなど。不溶性ばかりに偏らないよう注意
- 発酵食品を毎日摂る:味噌汁、キムチ、ヨーグルト、ぬか漬け、納豆などを習慣に
- 甘味料・添加物を減らす:特に「0カロリー飲料」やプロテインバーに含まれる人工甘味料に注意
腸はすぐに変わる場所ではありませんが、整うと全身の調子が連鎖的に良くなります。小さな積み重ねが最も効果的な“内臓のトレーニング”です。
ストレスと交感神経優位の悪循環

Photo by Lika Yer on Unsplash
トレーニングは交感神経を活性化させ、「戦闘モード」に入る行為です。それ自体は問題ありませんが、切り替えるタイミングがなければ交感神経はフル稼働し続けます。仕事や人間関係で緊張が続き、夜になってもスマホで頭が休まらない──そんな生活では、副交感神経(リラックス・回復モード)に切り替わらず、回復が追いつかなくなります。結果として、筋肉の修復だけでなく内臓や免疫の働きまで低下してしまいます。
起こりやすい不調のサイン
- 寝つきが悪い、途中で目が覚める
- 朝食が入らない、胃腸が重い
- やる気が出ない、疲れやすい、頭がぼーっとする
- 筋肉の張りが取れない、ケガが増える
整えるために取り入れたい習慣
- スマホは寝る1時間前に手放す
- 湯船にしっかり浸かる
- 寝る前にアロマや間接照明でリラックス空間をつくる
- 朝は深呼吸や軽いストレッチ、散歩でリズムを整える
- 思考をノートに書き出す(ジャーナリング)
一見すると筋トレとは関係のない習慣ですが、鍛えた体を回復させるための大切なスイッチになります。頑張る時間だけでなく、ゆるめる時間も意識的に取り入れてください。
→ 自律神経を整える方法は 『トレーニーの睡眠戦略|筋肉を伸ばすもうひとつの時間』で詳しく紹介しています。
急激な体型変化による皮膚の不調

Photo by Luiz Rogério Nunes on Unsplash
トレーニングや食事管理がうまくいくと、体型は短期間で大きく変化します。これは努力の成果ですが、皮膚がそのスピードについていけないことがあります。急激な増量では皮膚が引き伸ばされてストレッチマーク(肉割れ)が出やすくなり、急な減量では皮下脂肪と一緒に皮膚のハリも失われ、たるみやシワが目立つことがあります。ホルモンや皮脂分泌の乱れが重なれば、ニキビや肌荒れも起こりやすくなります。
起こりやすい不調のサイン
- 腕・肩・腹部・脚に赤紫〜白っぽい筋(ストレッチマーク)
- 皮膚がたるみ、引き締まらない
- ニキビや炎症、毛穴の目立ち
- 乾燥や赤みで敏感になる
整えるためにできること
- 急激な増減量を避け、月単位の緩やかな変化を目指す
- 入浴後の保湿ケア(オイルやクリーム)を習慣にする
- ビタミンC・E・コラーゲン・亜鉛などを意識して摂る
- 肌荒れが続く場合は糖質・脂質のバランスや腸内環境も見直す
皮膚の回復は筋肉よりも時間がかかります。成果を焦らず、皮膚の伸縮性も意識してケアしていきましょう。鍛えるだけでなく、守る・整えるという視点も大切です。
まとめ
筋トレに熱中するほど、数字や見た目に意識が向かいやすくなります。扱う重量、体脂肪率、腹筋の割れ具合──。ですがその裏で、便秘・肌荒れ・無気力・関節痛といった“不調”が静かに進んでいることもあります。
こうした不調は意志の弱さではなく、多くの場合は必要な栄養や休養が足りていないだけです。腸、肌、ホルモン、神経、免疫といった体の土台が整ってこそ、筋肉は本来の力を発揮できます。
トレーニーの不調には、トレーニーなりの原因と対策があります。気合いで乗り切るのではなく、自分の体を理解して整えること。それが長く強く鍛え続けるための近道です。
あなたの体は、正しく応えます。無理に追い込むより、今必要なケアを選びましょう。その積み重ねが、次の成長につながります。
NEXT STEP