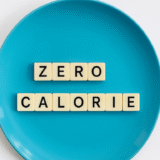痒み・イライラ・疲れ…それ、頑張りすぎのサインかも
減量に本気で取り組んでいると、ふとした瞬間に「いつもと違う自分」に気づくことがある。
なんだか情緒が不安定になる。肌が荒れる。やたらと疲れやすい。——これらはすべて、身体が今、何かを訴えているサインかもしれない。
トレーニングや食事管理が習慣化していても、心と体のバランスが崩れれば、パフォーマンスも結果も遠ざかっていく。
むしろ、その異変に気づけることこそが“整える力”なのかもしれない。
この記事では、減量中に起こりやすい不調とその背景を整理し、AGFらしい視点で対策と整え方を提案する。
よくある症状とその背景
感情が不安定になる(イライラ・落ち込み・焦燥感)

Photo by Людмила Покровская on Unsplash
減量期にありがちな変化のひとつが、情緒の乱れである。
理由は複数あるが、主に以下の3点が影響している:
- カロリー不足による神経系の過敏化
脳はエネルギーを大量に消費する臓器であり、摂取カロリーが落ちるとメンタルの安定にも影響が出やすい。 - 糖質制限によるセロトニン分泌の低下
幸福感をつかさどる神経伝達物質「セロトニン」は、糖質摂取によって合成が促進される。極端な糖質制限は、その働きを阻害してしまう。 - ストレスホルモン(コルチゾール)の上昇
身体にとって“減量=飢餓状態”であり、コルチゾールが慢性的に高まりやすい。この状態が続くと、不安や焦りを引き起こしやすくなる。
肌荒れ・かゆみが出る(とくに顔・背中・肘など)

Photo by Alexander Grey on Unsplash
一見、ダイエットと無関係に思える肌トラブルも、減量期には意外と多い。原因は以下の通り:
- 脂質の摂りすぎではなく、“脂質不足”
肌の潤いを保つには、一定量の良質な脂質が欠かせない。脂質を過剰にカットすると、皮脂バランスが崩れ、乾燥・炎症を招きやすくなる。 - 必須脂肪酸の不足(オメガ3など)
特にフィッシュオイルなどに含まれるEPA・DHAは、抗炎症作用を持つ。不足するとアトピー的な症状やかゆみが強く出るケースもある。 - ビタミン・ミネラルの欠乏
ビタミンA、B群、亜鉛などの栄養素は肌のターンオーバーや修復に関与する。減量により食材が偏ると、無意識に不足しやすい。
疲れが抜けない・だるさが続く
Photo by Pixels Of Life on Unsplash
トレーニングの質を維持しているのに、なぜか抜けない倦怠感。それも減量期特有のサインである。
- 単純な栄養不足
摂取カロリーが基礎代謝を下回るほど制限されると、身体は「省エネモード」に入り、動作が重くなりやすい。 - 睡眠の質の低下
ホルモンバランスの乱れや、夕食の糖質不足により、深い眠りに入りづらくなることがある。結果、翌日に疲れを持ち越してしまう。 - 自律神経の乱れ
過度なトレーニング、食事制限、精神的ストレス。このトリプルパンチで交感神経優位な状態が続くと、リカバリーが間に合わなくなる。
対策①:食事の見直し

Photo by Mark DeYoung on Unsplash
脂質は“切る”より“選ぶ”
脂質=太る、というイメージは根強いが、それは量と質の話を切り分けていないからである。
脂質はホルモン合成、細胞膜の構成、脳の働き、皮膚の保護といった生命活動の土台を支えている。減量中でも、極端に削るべきものではない。
特に意識したいのは、以下の脂質を適度に残すこと:
- オメガ3脂肪酸(青魚・えごま油・亜麻仁油など)
抗炎症作用があり、肌・メンタルの両方に効果的。毎日少量でOK。 - 一価不飽和脂肪酸(オリーブオイル・ナッツ類)
脂肪燃焼をサポートし、糖質との組み合わせでも太りにくい。 - 飽和脂肪酸も“最低限”は必要(卵・赤身肉・ココナッツオイルなど)
テストステロンの材料としても重要。完全カットは逆効果。
逆に、マーガリン・ショートニングなどの加工油脂や、揚げ物の残り油などは避ける対象としたい(加工油脂についてはこちら、トランス脂肪酸のリスクについてはこちらで詳述)。
糖質は“減らす”ではなく“整える”
糖質を敵視する人は多いが、減量中も必要最低限の糖質は残しておきたい。理由は以下の通り:
- 筋トレのパフォーマンス維持
- セロトニン合成(メンタル安定)
- 睡眠の質の確保(特に夕食後の微量糖質)
食物繊維を含む炭水化物(玄米、さつまいも、オートミールなど)を中心に、「量を減らす代わりに質を高める」意識を持つとよい。
サプリは補助、中心にはしない
マルチビタミンやフィッシュオイルなどのサプリは便利だが、それで食事のバランスを置き換えてしまうと、本質的な解決からは遠ざかってしまう。
あくまで“補うもの”としての位置づけを守ること。
土台にあるのは、バランスよく整えた日常の食事である。
対策②:生活リズムの最適化

Photo by Andrea Davis on Unsplash
睡眠の質こそ、減量の土台
減量中のパフォーマンスやメンタルの安定において、睡眠はトレーニングや食事と並ぶ最重要項目である。
特に意識したいのは以下の3点:
- 就寝2〜3時間前の軽い糖質摂取
糖質はセロトニン→メラトニンという睡眠ホルモンの流れをスムーズにし、入眠を助ける。 - 深部体温と入眠タイミングの調整
夕方以降に湯船に浸かることで一度体温を上げ、自然な放熱とともに眠りやすくなる。 - 寝る直前のブルーライト・興奮刺激を避ける
スマホや強い照明、SNSなどは神経を刺激し、交感神経を高めてしまう。
減量中はとくに睡眠が浅くなりやすいため、「時間」より「質」を重視した工夫が欠かせない。
トレーニングは“削る”のではなく“調整する”
疲労感やモチベーション低下を感じたとき、「減量中なのに自分は甘い」と責めてしまう人は多い。だが、それは逆である。
- 減量中は“回復力”が落ちている状態
普段通りの強度が逆効果になることもある。オーバートレーニングや免疫低下のリスクも見逃せない。 - 一時的に軽くする勇気を持つ
短期間だけでもボリュームや強度を落とし、“整える週間”を挟むことでむしろ調子が戻るケースは多い。 - NEAT(非運動性熱産生)を活用する
意図的な筋トレを減らしても、散歩や家事などの活動量を保てば、総消費カロリーは十分に確保できる。とくに歩く習慣は、おすすめだ(詳しくはこちら)。
トレーニングは「削る」ものではなく、「整える」もの。心身の状態に合わせて柔軟に調整する視点を持ちたい。
ストレスを溜めない仕組みをつくる
減量に限らず、すべての体調不良の影にストレスあり。
だからこそ、コントロールではなく“逃がす仕組み”が重要になる。
- 光を浴びる、植物に触れる、自然音を聴く
人間の神経系は“自然との接触”に対して明確なストレス緩和反応を示す。 - 人と話す/書き出す/音楽を使う
感情を「溜めない」ルートを意識的に持つことで、精神的な余白が生まれる。 - SNSとの付き合い方を見直す
他人の身体・食事・成果に触れすぎると、“自分の減量”がブレてくる。意識的な距離感も必要である。
減量中は「がんばっている自分を支える仕組み」を、自分で設計していくことが鍵になる。
減量は“削る”だけではない
減量=削る、というイメージは根強い。
実際、食事量を減らし、脂肪を落とし、数字を下げていくプロセスではある。
だが、削るだけでは続かない。
身体だけでなく、心までも削ってしまったとき、多くの人が減量に挫折する。
本来の減量とは、「不要なものを手放し、必要なものを残す」行為である。
それは単に体脂肪の話にとどまらず、生き方や習慣、思考の整理でもある。
食事も、生活も、心の状態も。
削るだけでなく、整えることで“続けられる減量”が形になっていく。
まとめ

Photo by Red Reyes on Unsplash
減量中の不調は、単なる副作用ではなく、身体からのサインである。
そのサインに気づき、立ち止まり、対策を講じることは、ただの健康維持ではない。
それは、「自分の身体と真剣に向き合っている証拠」だ。
減量は自分を苦しめるためのものではない。
整えながら進む——その選択肢を、AGFはこれからも静かに支えていく。
NEXT STEP