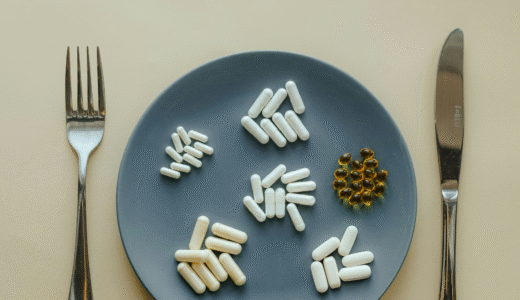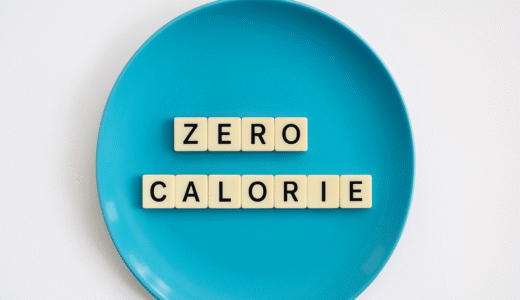整える食生活は、“うまみ”とも向き合う
「うまみ」。誰もが好きな味だが、その正体を知っているだろうか。
実は、私たちの味覚には、人工的に「おいしさ」を作り出す調味料がしれっと入り込んでいる。
毎日なにげなく食べている加工食品。そのおいしさの裏側にあるものを、少しだけ覗いてみよう。
うまみ調味料とは何か

Photo by Karyna Panchenko on Unsplash
いわゆる「うまみ調味料」は、食品にうまみを加えるために使われる調味料だ。
もっとも有名なのはグルタミン酸ナトリウム(MSG)。
中華料理に使われる「味の素」を思い浮かべる人も多いだろう。
最近では、あからさまに「うまみ調味料」とは書かれず、「調味料(アミノ酸等)」「たん白加水分解物」などと表示されていることが多い。
名前は変わっても、目的は変わらない。強いうまみで「おいしく感じさせる」ための技術だ。
含まれる成分と仕組み

Photo by Olya P on Unsplash
うまみ調味料には以下のような成分が含まれていることが多い:
- グルタミン酸:昆布などに含まれるうまみ成分
- イノシン酸:かつお節や肉に含まれる
- グアニル酸:干ししいたけ由来のうまみ
これらは単体でもうまみを感じるが、掛け合わせることで相乗効果が生まれ、より強烈な味覚刺激となる。
一度この人工的なうまみに慣れると、素材本来の味では物足りなく感じるようになる。
何が問題視されているのか

Photo by tommao wang on Unsplash
うまみ調味料そのものが悪というわけではない。
ただ、使い方や頻度によっては、次のような影響が出ることもある。
- 味覚が鈍くなる。強いうまみに舌が慣れ、素材本来の味を感じにくくなる
- 依存的な食習慣。加工食品に頼りがちになり、自然な味では満足できなくなる
- 食のバランスが崩れる。「うまければOK」になり、塩分や脂質の摂りすぎにつながる
かつて「中華料理症候群」として、MSGの摂取後に頭痛やしびれを訴える症状が話題になったこともある。
現在では明確な因果関係は否定されているが、体質的に合わない人がいるのも事実だ。
食品表示の見方

Photo by Brad on Unsplash
うまみ調味料を避けたいときは、以下のワードを原材料表示でチェックしてみよう:
- 調味料(アミノ酸等)
- たん白加水分解物
- 酵母エキス
- グルタミン酸Na(ナトリウム)など
とくに注意したいのは、「無添加」や「自然派」と書かれた商品にも別名で含まれているケース。
パッケージの印象に頼らず、裏面の表示を確認する習慣が大切だ。
AGF的“整える”視点

Photo by Yu Hosoi on Unsplash
うまみ調味料を完全にやめる必要はない。
ただ、それが入っていないと満足できない状態になっているなら、少しだけ立ち止まってみる価値がある。
- だしを自分でとる
- 素材の味を味わう
- 塩や醤油など基本調味料の質を見直す
- 「なんとなく物足りない」と感じる感覚に気づいてみる
味覚も筋肉と同じように、鍛え直すことができる。
最初は地味に感じるかもしれないが、自然な味の豊かさに気づけるようになる。
おいしい。でも、もったいない
正直に言えば、うまみ調味料はおいしい。
ただ、それがないと満足できない舌になっているとしたら──それは少しもったいない。
知らずに摂り続けるのではなく、知ったうえで選ぶ。
それだけでも、食生活は整っていく。
NEXT STEP