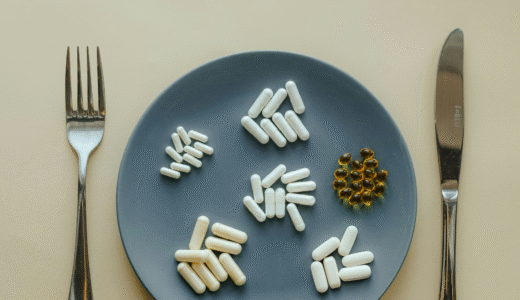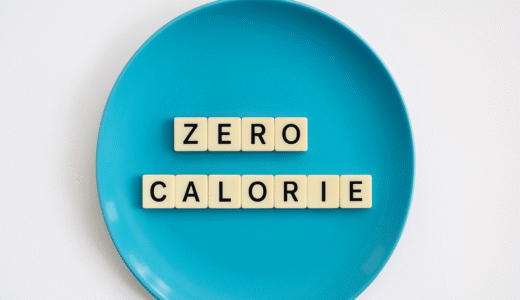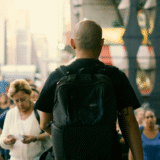その色と香り、“美味しさ”じゃなく“演出”かもしれない。
──その「美味しそう」、どこから来てる?
コンビニのスイーツが美味しそうに見える理由。
スポーツドリンクの爽やかな香りに惹かれる瞬間。
──それって、本当に“素材”の力なんだろうか?
トレーニングを習慣にし、食事の質を見直すようになると、
「高タンパク」「低脂質」「無添加」といったワードに自然と敏感になっていく。
でも実は、見落とされがちな添加物がある。
それが、「着色料」と「香料」だ。
着色料・香料とは?|視覚と嗅覚を“演出”する添加物
着色料や香料は、食品そのものの「質」を変えるものではない。
色や香りといった“印象”を整えるために使われている。
- 見た目を鮮やかにして、購買意欲を刺激する
- 加熱や保存で失われた風味や色を“補う”
- フルーツ味・バニラ味・焼き立て感などを“再現する”
合成着色料(赤40、青1、黄4など)や、人工香料(エチルバニリン、アセトアルデヒドなど)は
「コストが安く、効果が強い」ため、加工食品に頻繁に使われている。
なぜ「整えたい人」が気をつけるべきか?

Photo by Edgar Chaparro on Unsplash
たとえば──
- 果汁が1%未満なのに「濃厚フルーツ味」のゼリー
- 焼いてないのに“香ばしい”香りがするパン
- 味は薄いのに“食べた気になる”サラダチキン
これらは、視覚と嗅覚に訴えかけることで“満足感”を演出している。
でも、それは身体にとっての本当の満足とは限らない。
過剰な香料や色素は、以下のような“感覚のズレ”を生む可能性がある:
- 味覚の感受性が鈍る → 素材の自然な甘さや旨味を感じづらくなる
- 香り=報酬と錯覚 → 食べても栄養が足りないのに、満たされた気になる
- 加工食品への依存性が高まる → 自然な食材では“物足りなさ”を感じるように
その結果、食事の質を整えるつもりが、
知らず知らず“加工品に頼る習慣”を深めてしまうこともある。
食品表示での見つけ方|“色・香り”の裏にあるキーワード

Photo by Franki Chamaki on Unsplash
着色料と香料は、原材料表示の中で以下のように記載されていることが多い:
✔ 着色料
- 「赤○号」「黄○号」「青○号」など(例:赤40、黄4)
- 「カロチノイド」「クチナシ色素」など天然系もあるが、使用量や製法にはばらつきあり
✔ 香料
- 多くは「香料」としか記載されず、成分の内訳は非公開
- 「果実風味」や「バニラ香料」なども、実際は合成の場合が多い
つまり、「果汁」や「天然」の記載がなければ、人工的に作られた香り・色の可能性が高い。
完全回避より、“感覚を整える”選択を

Photo by Yu Hosoi on Unsplash
着色料や香料は、“毒”ではない。
ただし、“整えたい身体”にとっては、五感の感受性を乱す要因にもなり得る。
だから大切なのは、「全部避けること」ではなく、感覚のバランスを取り戻すことだ。
- 甘さや香りが強い加工品は、週末の“ご褒美”に
- 普段の食事は、素材に近い味・色・香りを選ぶ
- 疲れた日や外食が続いた後は、出汁や果物などで“味覚リセット”
嗅覚と味覚が整えば、自然と「本当に体が欲しているもの」に気づきやすくなる。
まとめ

Photo by Юлия Заковеря on Unsplash
見た目や香りで「美味しそう」に思える食品が、
実際の栄養価や満足度と一致しているとは限らない。
トレーニーにとって重要なのは、
身体の声を聞くセンサー=味覚・嗅覚を鈍らせないこと。
今日の1食で、“刺激の強さ”ではなく“整いの深さ”を選んでみよう。
その積み重ねが、集中力・コンディション・筋肉の成長を支えていく。
NEXT STEP