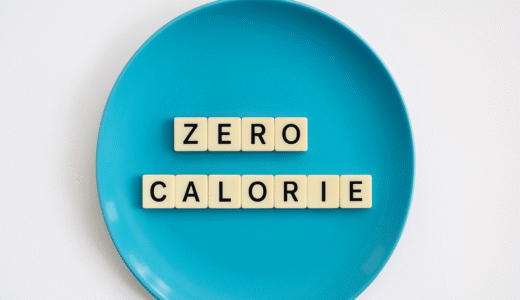──「体にいい」の前に、「避けたい」を知る
“健康志向”が落とし穴になるとき
食事に気を遣い始めたとき、私たちは「何を食べるか」という視点に加えて、「何を避けるべきか」という視点も必要になる。
たとえば“ゼロカロリー”という言葉。なんとなく良さそうに感じるが、その裏には人工甘味料や加工油脂、添加物など、体を整えることから遠ざける成分が隠れていることもある。
もちろん、すべてをすぐに手放す必要はない。
ただ、成分の正体や仕組みを知っておくことで、自分の軸で選べるようになる。
このページでは、AGFとして避けた方がよいと考える成分や食品を、理由とともに一つずつ紹介していく。
すべてのピースが揃ったとき、あなたの選択はもっと自由で、整ったものになっているはずだ。
加工された素材と成分は“別物”──たとえば加工油脂とトランス脂肪酸
この特集では、いわゆる“食品添加物”だけでなく、加工された素材や、その中に含まれる成分も扱っている。
加工油脂(ショートニング・植物油脂など)は、食品表示に記載される“素材名”であり、
トランス脂肪酸は、その中に含まれている可能性のある“脂肪酸(成分)”である。
言い換えれば──
加工油脂という“容器”の中に、トランス脂肪酸という“中身”が入っているかもしれない。
両方を取り上げるのは、食品表示の読み方だけでなく、その裏に潜む成分や体への影響まで深く知ったうえで、選んでほしいからだ。
人工甘味料(アスパルテーム・スクラロースなど)

Photo by Alexander Schimmeck on Unsplash
甘くてカロリーゼロ。そんな言葉に惹かれて、気づけば「毎日何かしら摂っている」という人も少なくない。
だが、その“ゼロ”の代償として、神経系や腸内環境に影響を及ぼす可能性があることは、あまり知られていない。
甘さはあるのにカロリーがない──。
それは脳にとって“不一致”であり、満足感や食欲調整を狂わせることがある。
さらに一部の人工甘味料には、うつ症状や興奮性、頭痛との関連が指摘されるケースも。
メンタル・神経系・腸内環境への影響
→ 記事リンク:[ 人工甘味料|ゼロカロリーの甘い罠 ]
トランス脂肪酸(マーガリン・ショートニングなど)

Photo by Mustafa Bashari on Unsplash
常温でも固形を保ち、食品の風味や保存性を高める──そんな“便利”さの裏にあるのが、トランス脂肪酸。
この脂質は、悪玉コレステロール(LDL)を増やし、動脈硬化や心疾患のリスクを高めることが多くの研究で明らかになっている。
欧米では使用が制限され、全面禁止の国もあるが、日本では表示義務もないまま流通している。
“見えない脂質”こそ、知っておきたい。
→ 記事リンク:[ トランス脂肪酸|美味しいのに、身体が重い理由 ]
加工油脂(植物油脂・酸化油など)

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash
「植物性=ヘルシー」と思い込んでいないだろうか?
実際は、リノール酸などのオメガ6系脂肪酸が多く含まれる加工油脂をとりすぎることで、体内の炎症を促し、ホルモンバランスの乱れにつながることもある。
さらに、古い油や高温加熱によって酸化した油は、細胞を傷つけ、慢性疲労や老化を加速させる原因にも。
“ヘルシー風”の表示に、注意したい。
オメガ6過多・慢性炎症・ホルモンバランス
→ 記事リンク:[ 加工油脂|“植物性”の落とし穴に気づけるか? ]
リン酸塩(インスタント食品・加工肉など)
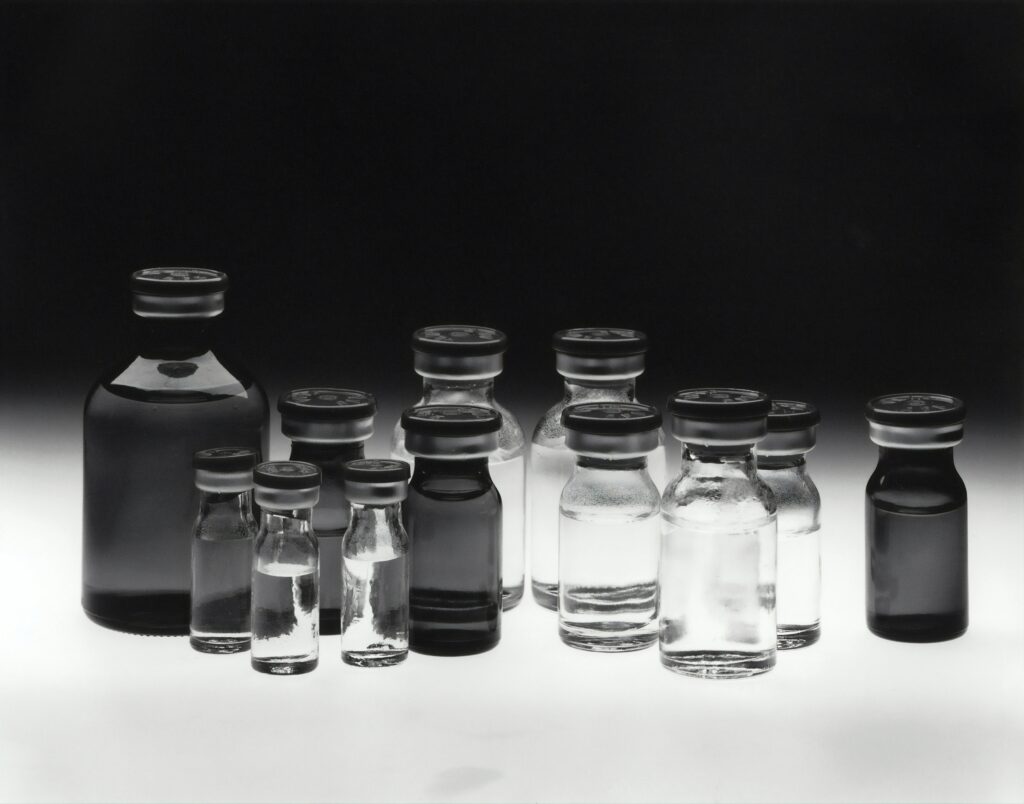
Photo by National Cancer Institute on Unsplash
加工食品の食感を良くしたり、色を鮮やかに見せたりするために使われるリン酸塩。
しかし過剰に摂取すると、カルシウムなどミネラルの吸収を阻害し、骨や歯への影響が懸念される。
また、腎機能への負担も報告されており、特に腎疾患を持つ人は注意が必要だ。
問題は、“どれだけ摂っているのか分かりづらい”こと。
→ 記事リンク:[ リン酸塩|筋肉が育たない“隠れブレーキ” ]
着色料・香料(赤色40号・人工フレーバーなど)

Photo by Luis Aguila on Unsplash
カラフルなお菓子やジュースに使われる合成着色料。
「見た目を良くする」だけでなく、購買意欲や食欲を刺激する効果もあるが、それが脳や体にどう影響するかは見過ごせない問題だ。
赤色40号など一部の色素は、ADHDやアレルギー症状との関連性が指摘されており、海外では使用が制限されているものも。
香料もまた、“何がどれだけ入っているのか分からない”という点で、選ぶ際の判断を難しくする。
→記事リンク:[ 着色料・香料|“美味しそう”の裏にある違和感 ]
うま味調味料など(グルタミン酸ナトリウム)

Photo by Franki Chamaki on Unsplash
「うま味」が強いと、それだけで美味しく感じる。
だが、その快感が強すぎると、脳が“依存状態”に近づくことがある。
グルタミン酸ナトリウム(MSG)は、適量であれば問題ないが、大量摂取で興奮性や頭痛、さらには満腹中枢の異常を招くリスクが指摘されている。
自然の出汁とは異なり、“化学的に再現されたうま味”には注意が必要だ。
自然なうま味との違いとは?
→ 記事リンク:[ うまみ調味料|隠し味に潜む“味覚のリセットボタン” ]
“ゼロ系”食品(糖質ゼロ・脂質ゼロの落とし穴)
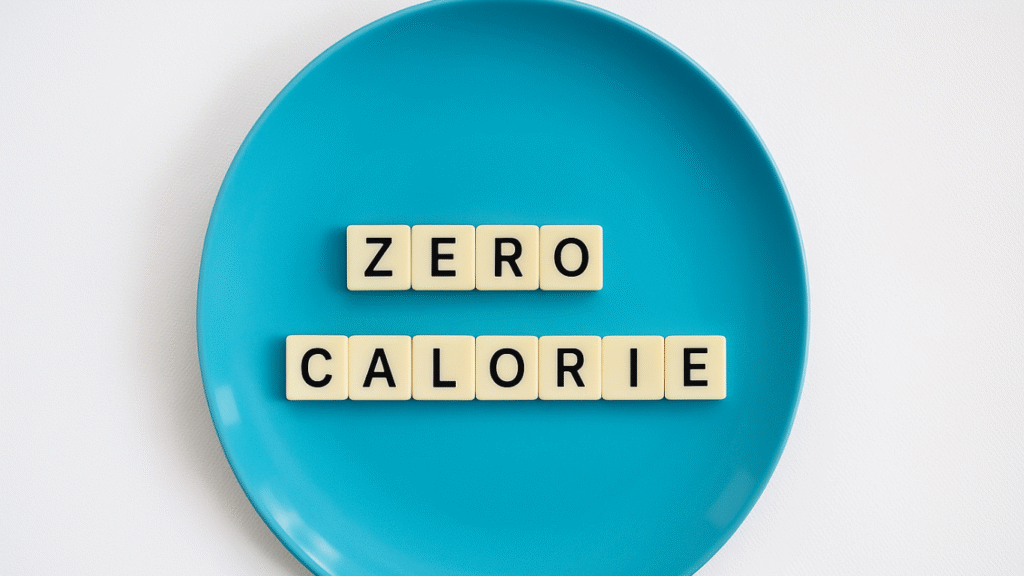
「ゼロ」と書かれていれば、なんとなく“健康そう”に見える。
しかし栄養表示の“ゼロ”には、「一定量未満であればゼロと表示してよい」というルールがある。
つまり、完全にゼロではない場合もある。
また、本来あるべき栄養素を削りすぎた結果、満足感の低下や代謝の低下など、逆効果になることも。
“数字”ではなく、“整うかどうか”で判断したい。
→ 記事リンク:[ ゼロ食品|“数字だけ”を信じるな ]
保存料(ソルビン酸、パラオキシ安息香酸など)

Photo by Brad on Unsplash
食品の腐敗を防ぎ、長持ちさせてくれる保存料。
しかしその便利さと引き換えに、腸内細菌のバランスや代謝、ホルモン分泌に影響を与える可能性があるといわれている。
特に毎日口にするような食品に含まれていると、知らないうちに積み重なってしまうのが怖いところ。
体内で何が起きているのか──想像しながら、選ぶ習慣を。
→ 記事リンク:[ 保存料|日持ちの裏にある“見えないもの” ]
まとめ
これは「食べてはいけないもの」を列挙したリストではない。
目的は、「何を避けるか」という視点を持ち、自分を整える選択ができるようになることだ。
すべてを一度に変えようとしなくていい。
ただ、「こういう成分があって、こういう影響があるかもしれない」という情報を知っておくだけで、次に何かを選ぶときの軸になる。
完璧である必要はない。
少しずつでも、自分の体と向き合いながら、“本当の意味で体にいい選択”を育てていこう。
NEXT STEP