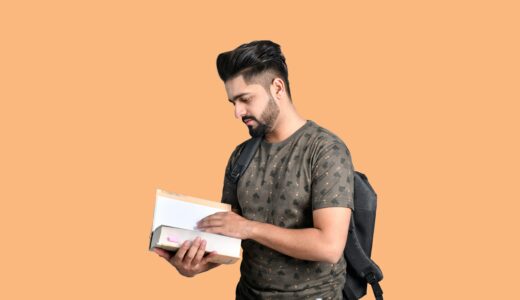──トレ中“音あり/なし”の使い分け方
“音楽を聴く”のが当たり前になっている今こそ
ジムに入ると、多くの人がイヤホンをしている。
音楽はテンションを上げ、気分を切り替えてくれる。今や、それはトレーニングの一部と言ってもいい。
でも実際のところ、音楽ってどれくらいトレーニングに効果があるのか?
逆に、無音でのトレーニングにはどんな意味があるのか?
今回は科学的なデータも踏まえながら、「音楽あり/なし」の違いと、それぞれの使い分けについて整理していこう。
1. 音楽の効果|科学が示す“感情・集中・持続”への影響

Photo by Anna Keibalo on Unsplash
モチベーションUP・気分の向上
音楽が感情を動かすのは、多くの研究でも示されている。特にテンポの速い音楽や、好きな曲は気分を高め、前向きなエネルギーを引き出すとされる。
・疲労感(RPE)の軽減
RPE(自覚的運動強度)という指標があるが、音楽を聴いているとキツさを感じにくくなることがわかっている。脳が別の刺激に注意を向けているため、疲労の意識が薄れる効果がある。
・パフォーマンスの向上
反復回数、維持力、テンポの安定など、特にレジスタンス運動(筋トレ)や有酸素運動で効果的。最大筋力(1RM)にはあまり影響しないが、セット数や集中維持に好影響を与える。
・好きな曲(自己選択型)が効果的
研究によると、「自分が選んだ音楽」のほうが、モチベーション・気分・持続力すべての点で高い効果を示す。つまり、プレイリスト選びも立派な“設計”だ。
2. 無音のメリット|身体と向き合う“静かな時間”

Photo by Jaiden Peters on Unsplash
・集中力が高まりやすい
音楽を聴かないことで、フォーム・筋肉の感覚・呼吸に意識を向けやすくなる。特に技術向上を目指す時や、重量が上がったフェーズでは「感覚に集中できる環境」が武器になる。
・自分の状態に気づきやすい
“今日はなんとなく気持ちが落ちている”
“疲労が残ってる”
──そんな微細な感覚は、静かな環境の方が見えやすい。無音は、身体との対話の時間でもある。
・音への依存を手放せる
どんな状況でも集中できる人は強い。無音でのトレーニングは、精神的な自立心や回復力を養う手段にもなり得る。
3. シーン別ガイド|音あり/なしの使い分け

Photo by Ian Taylor on Unsplash
| シーン | おすすめ |
|---|---|
| 疲れてる日 | 音楽あり(モチベUP) |
| テンションを上げたいとき | 音楽あり(リズムで加速) |
| 集中したい・技術を意識したい | 音楽なし(静けさを活かす) |
| 原点に戻りたいとき | 音楽なし(芯を整える) |
音楽は、あくまで“手段”。
どちらが優れているかではなく、どう使い分けるかが鍵だ。
4. AGFの視点|“選ぶこと”が、習慣の芯をつくる
「なんとなく音楽を流す」のではなく、「目的に合わせて選ぶ」
音楽を使うのも、静けさを選ぶのも、トレーニング設計の一部。
自分の状態を見て、「何が必要か」を選べる人になる。
音で勢いをつけたい日もあれば、静けさの中で芯を整えたい日もある。
大切なのは、“流されないこと”。
選ぶことで、自分の在り方が定まっていく。
音を選ぶとは、「どう在るか」を選ぶこと。
AGFは、そういう選択の積み重ねを“強さ”だと考えている。
音に頼る日があってもいい。
でも、「いま、どちらを選ぶか?」という視点だけは、忘れずにいたい。
まとめ

Photo by Brad Neathery on Unsplash
音楽は、トレーニングを支えてくれる強力なツール。
だが、気づけば“音がないと落ち着かない”状態になっていることもある。
音も静けさも、自分にとって必要なら使えばいい。
大切なのは、無意識に流されないこと。
芯を持って選ぶ。
それが、すべての習慣に通じる“強さ”になる。
音を選ぶことは、“どう在るか”を選ぶことだ。
NEXT STEP